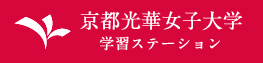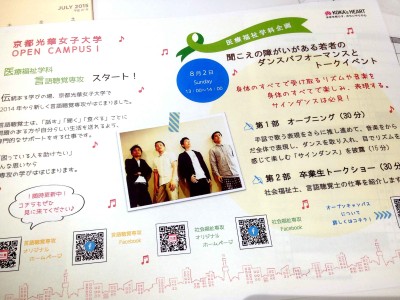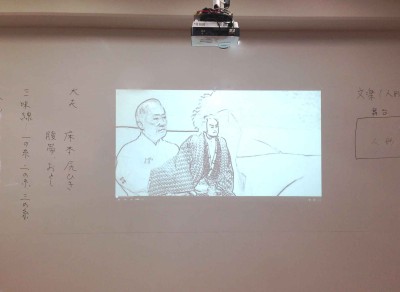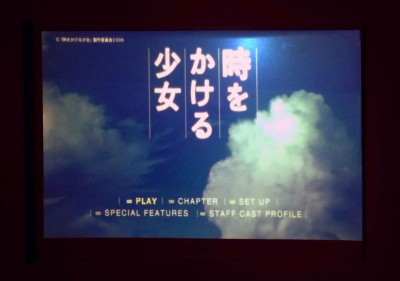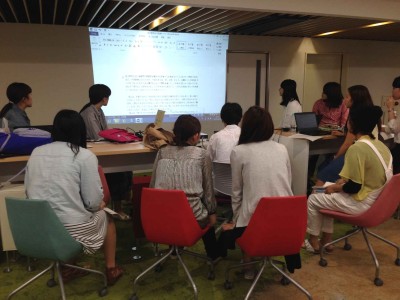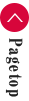カナダのリジャイナ大学より、留学生の方が来られているのですが、
ラーニングルームで日本の伝統芸能「人形浄瑠璃」について学ばれていたので、
staff:hも参加させていただきました。

今度本学の学生や先生方と一緒に、大阪にある文楽劇場に鑑賞しに行くそうで、
その前に、ひと通りの知識を学んでおかれるのだとか。
実は私も、興味を持っていながらも、なかなかチャンスに恵まれず、
生で人形浄瑠璃を見たことがありません。
想像ではありますが、小道具の細やかな装飾や、太夫の声の響きなど、
恐らく生で見るのとでは迫力が全然違う様に感じます。
人形浄瑠璃は、
「太夫」(語り)、「三味線」、「人形」という3つの役割からなされます。
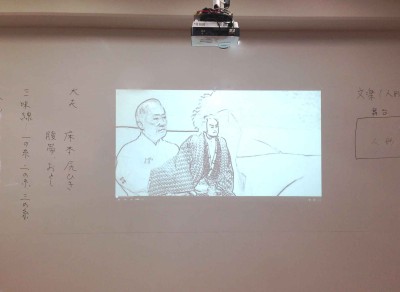
皆さんご存知だとは思いますが、
「人形」のみ、1つの人形を3人掛かりで動かす為、
関節などの細かい動きを表現することができ、
人間らしい動作や心情を表すことができます。
足の動きを習得するだけで10年の修行を要すると言われています。
また、普段はかしら、かつら、胴体、衣装、手足と、
それぞれ保管されているそうなのですが、
公演の都度、人形師が髪を結うなどして
登場人物に合わせて人形をしつらえるのだとか。
そういった事からも愛情が注がれていることが分かり、
人形に魂が宿っているように見える理由なのかもしれません。
テーマとなっている語り物自体も、
一見難しそうに感じるかもしれませんが、
人間らしい心情を描いたお話が多いそうなので、
少し予習をしていけば、海外からお越しの方でも充分に楽しめると思います。
リジャイナの皆さんも、日本が誇る伝統芸能であることに納得している様子でした。
是非楽しんできてください。
✍staff:h