3月17日(金)は卒業式でした。
4年生の皆様、ご卒業おめでとうございます。
当日は、たくさんの学生さんが学習ステーションに来てくれました。
とても綺麗~!!
彼女たちと、いろいろなお話しをしたことを思い出します。
少し寂しい気持ちにもなりましたが、卒業というみなさんの大きな節目に携わり、
晴れ姿を見ると、嬉しさでいっぱいになりました。
これからの社会人としてのご活躍をお祈りしています。
たまには学習ステーションまで顔を見せに来てくださいね。
✍staff:k
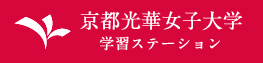
学習ステーションからのお知らせ・イベント情報・ブログをご紹介

早いもので3月も半ばを過ぎ、平成28年度もあとわずかとなりました。
明日3月17日は、卒業式です。
看護学科の4年生は、2月に国試を終え、たまに学ステにきても、みんなで集まり、謝恩会の準備をしています。
その一方で、管理栄養士専攻の4年生は、卒業式後の3月19日に国試があります。
そのため、学ステでは、ほぼ毎日、朝から晩まで、国試受験に向けて学習に取り組む学生の姿が見られます。
彼女たちには、今まで勉強を続けてきた自分の力を信じ、「必ず、合格する」という自信をもって国試に臨んでもらいたいです。
さて、先日3月6日、学習ステーションの企画として、
「看護師・助産師養成課程の4年生・3年生 『国試を語る』・『実習を語る』」を開催しました。
この企画は、看護学科2年生の学習ステーションピア・サポーターが呼びかけ、
4年生・3年生の先輩ピア・サポーターから「国試」、「実習」について話を聞こうというものです。
当日は、4年生には、卒論や国試について、
3年生には、実習と実習に向けての準備について、話しをしてもらいました。
4年生は、受験したばかりの今年の助産師と看護師の国試問題を持参、
今までと変わった点などについて詳しく説明し、
さらに、国試に向けての学習の方法について話してくれました。
3年生からは、実習中は「怒られて当たり前!」や「聞く勇気がとても大事」などの言葉があり、
2年生は、実習に向けての心構えを教わることができたようです。
✍staff:k
今週、16日(木)に助産師の、17日(金)に保健師の、そして19日(日)には看護師の国家試験が行われます。
看護学科の学生にとって、今週は大学での学びの集大成のときと言えると思います。
学ステでは、毎日、朝早くから夜遅くまで、国家試験の勉強に頑張る4年生の姿が見られます。
今日も朝から、オープンスペースで、学習ラウンジで、グループ学習ルームでと、
それぞれにお気に入りの場所で、一人あるいは集まって自学習に取り組んでいます。
問題の出し合いをしたり、苦手な所を振り返ったり…。
見ているとあっという間にホワイトボードを使い、ポイントをまとめていきます。
グループ学習ルームを、まるで自分の家の勉強部屋のように使っています!(笑)
ほぼ毎日のように、この部屋に集まって自学習をしていた彼女たちの姿を見るのも、あと少しとなりました。
私は今年から学ステに来ましたが、いつの頃からか、
彼女たちが朝、グループ学習ルームの鍵を借りに来るのが習慣になったようで、
来ない日は風邪でも引いたのかと心配になるほどでした。
彼女たちも、19日(日)看護師の国家試験を受験します。
1年間、本当に早かったなと思います。
看護師の国家試験が終われば、来月には管理栄養士の国家試験が行われます。
学ステは、頑張ってきた君たちの姿をずっと見てきました。
頑張ってきた自分に自信を持って試験に臨んでください。
大丈夫、結果は必ずついてきます。
最後まで諦めず、落ち着いて、自分の力を出し切ってください。
応援しています!
ファイト!!!
✍staff:k
1/11(水)~1/20(金)の間、後期定期試験に向けて、
学習ステーションのピアサポーター(先輩学生)が学習相談会を行いました。
学習相談会には計約50名の学生が参加しました。
参加した学生は、後期試験のことや学習内容でわからないことなどを真剣に質問し、
ピアサポーターの先輩は、それにわかりやすく答えていました。
学習相談会では、勉強の話以外にも実習のことなどいろいろな話を交えられ、楽しく行われてました。
1/26(木)から後期の定期試験が始まりました。
学ステで勉強する学生は本当に真剣ムード一杯です。
先週、インフルエンザにかかり休んでいた学生も今週からは元気に登校、
朝から学ステに来て長い時間、遅れを取り戻すかのようにみんなで集まって勉強に取り組んでいます。
後期末の時期は、試験に向けての学習だけでなく、多くのレポート課題が課されます。
みなさん、時間を最大限、有効に利用し、レポートと定期試験を乗り切ってください。
学ステは平日21:00まで、土日は17:00まで開いています。
PCも、平日21:00まで、土日は17:00まで借りることが出来ます。
分からないことがあれば遠慮なく聞きに来てください。
スタッフも、皆さんのサポートが出来るよう、頑張ります。
✍staff:k
1月11日(水)より学習ステーションにおいて、ピア・サポーター(先輩学生)による
後期末定期試験対策の学習相談会を開始しました。
1年の締めくくりである後期末試験が、1月27日から始まります。
この時期は課題が一気に増え、同時に試験に向けての勉強をしなければならない、
みなさんにとって本当に苦しいときですね。
学習相談会では、ピア・サポーターが、
みなさんのわからないところを共に考え、一人ひとりの質問に丁寧に答えてくれます。
また、自分の経験をもとに試験に向けての学習のポイントをアドバイスしてくれます。
現在、学習相談会に多くの1、2年生が参加しています。
先輩の言葉を一言も聞き落さないよう、メモもとる姿はとても真剣です。
それに応えて、ピア・サポーターは、ホワイトボードなどを駆使して
全員に分かってもらえるよう全力で取り組んでいます。
学習相談会は、1月20日(金)まで行います。
学科・専攻ごとの日程、場所は、光華ナビですでにお知らせしましたが、
学習ステーションHPのブログや学習ステーション内に掲示しています。
確認をしてください。
また、この機会に学生生活で悩んでいることや疑問に思っていることなど、
試験のこと以外でも気軽に相談ください。
みなさんのお越しをお待ちしています。
✍staff:k
11月28日(月)14:30から約1時間、学習ステーション内ラーニングルームにて、
第一回レインボープロジェクト企画「嚥下食ってなに?」が開催されました。
言語聴覚専攻、看護学科、管理栄養士専攻の3学科・専攻から20名の学生が参加しました。
最初に今回のプロジェクトの企画者である管理栄養専攻2年生の中根静香さん、谷咲音さんの2人から
嚥下の仕組みや摂食嚥下障害についての説明がありました。
続いて、医療現場における課題について学科・専攻を越えた参加学生の間で学び合いが行われました。
その後、中根さん、谷さんの2人が「おいしく、見た目にも美しい」の視点に立って調理してきた
嚥下調整食の試食会が行われました。
試食後に、一人ひとりが感じたこと、考えたことを述べ、全員で共有する時間がとられました。
参加した学生は皆、今回の嚥下調整食が見た目も味も良いことにとても驚いていました。
また、言語聴覚専攻や看護学科の学生の中には、
実習の際、実際に患者さんが嚥下調整食を食べる様子を見たという学生もいて、彼女たちからは、
・嚥下食は見た目も味も良くないから、食べたいと思わなかった。
・嫌がる患者さんに無理やり食べさせていて、介助する方も辛い…
私達も食べることを楽しみに生きているのだから患者さんは尚更だと思う。
・このような、食べたいと思えるおいしい嚥下食が広まればいいな
といった意見が出てきました。
どの専門職を目指す学生も「おいしく食べて欲しい」という共通の思いがあるのですね。
今回の企画を通して、どのような人にも”おいしく食べて頂く”という願いを叶えることは大切なことであり、
そのためにも職種間の連携は非常に重要だということが確認できたようです。
参加した学生の多くから「今後も多職種共働の勉強会をして欲しい」、「是非参加したい」などの声が聞かれ、
今回の企画を主催した中根さん、谷さんの2人は大変喜んでいました。
学習ステーションでは、今後もレインボープロジェクトの取組みについて、
皆さんにお伝えしていきます。
✍staff:k
10/31(月)、11/7(月)の2週にわたり、健康栄養学科管理栄養専攻の3年生が、
聞光館1階光庵横と3号館地下1階食カフェでグループごとに、
栄養教育論実習Ⅱの授業の一環で「食育」についての発表を行ったそうです。
学習ステーションでは、その指導に先立ち、発表の前週から連日、
何度も何度も練習を繰り返す学生の姿が見られました。
「どう説明すればもっとわかりやすくなるか」みんなで議論を繰り返し、
また、わかりやすくするためにかわいい絵を使うなど、
いろいろと工夫が施されていました。
この日、話を聞いたグループは、11/7(月)3号館で糖尿病についての指導をするとのことでした。
どんな食生活をすると糖尿病になるの?
遺伝はするの?
食事療法で治るの?
糖尿病の薬ってどんなものがあるの?
・・・・など。
頑張ってください!
✍staff:k
11月2日(水)の昼休み、管理栄養士専攻所属の学生を中心に、
学科を越えて4名の学生が集まり、話し合いが行われました。
中心となる管理栄養士専攻の学生は、栄養学での学びを通して、
栄養士だけでは解決できない多くの課題があると感じたそうです。
嚥下障害のある方の食事を例にすると、
その方の食べることのできる形態の献立をたてて提供するのは管理栄養士、
食事の介助は看護師やヘルパー、
嚥下機能の評価や、食べやすい食事姿勢を整えるのは言語聴覚士。
他の職種と意見を交わすことで、見える世界が広がるはずだと。
京都光華女子大学には医療・福祉系の多くの学科があるのに、
今まで学生間の横のつながりはあまりなかった。
そこで、彼女は、それぞれの仕事を知らないままに卒業するのはもったいないと感じ、
学生の間に多職種共働の取り組みができればと考えたとのことです。
集まった他学科の学生も、多職種連携のプロジェクトに興味を持ち、
この日は、今後どのように展開していくかが話し合われました。
この集まりを「レインボープロジェクト」と名付けたのは、
話し合いの日の朝、綺麗な虹が出ていたこともあり、
また、多職種をレインボーの色で表そうという意味を込めてだそうです。
一回目は管理栄養士専攻が担当し、嚥下食調整食の試食会を行うとのこと。
試食を通して、感じたことを発表する事で、
専門的な視点の違いを知り学ぼうと考えているとのことです。
今後は、このような会のときに、疑問に思ったことや知りたいことをリサーチし、
次回のテーマにしていきたいとのこと。
テーマに合わせて担当の学科を決め、勉強会の準備をしていく予定だそうです。
この学科の枠を超えた学生主体のプロジェクト、これからが楽しみです。
学習ステーションでは今後も応援していきます。
✍staff:k